“達人”塩田剛三 マイクタイソンやケネディのボディガードを投げ、世界を驚かせた神業!
塩田剛三
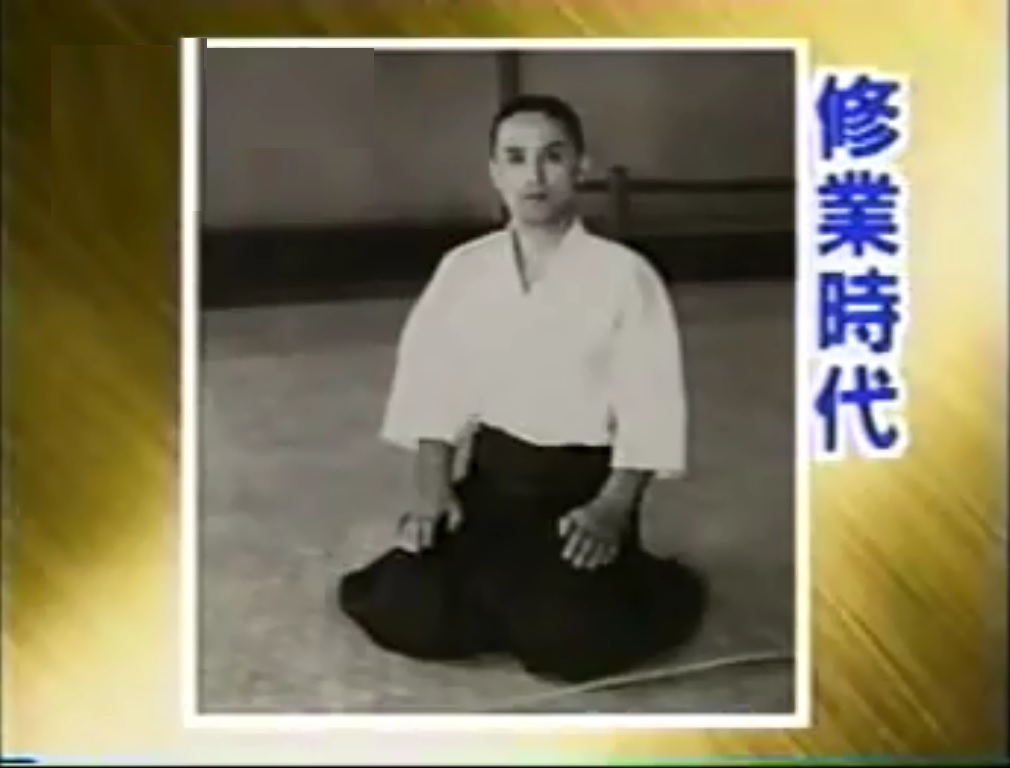
ある意味で格闘技、バトル漫画の最高峰とも言える範馬刃牙、その登場人物のモデルとして最も有名とも言える人物かもしれない。
渋川剛気。
身長155センチ、体重47キロ、女性とも見まごうばかりの小柄な体格にして、その洗練され、研ぎ澄まされ、究極の領域に達した業により、自分よりも一回りも二回りも、ジャックハンマーのような2メートルを超える巨大な男相手にしても、まるで赤子の手をひねるかのように投げ、ひっくり返し、飛ばしてきた、文字通り達人として描かれるキャラクターだ。
私もそのあり方、戦い方、立ち居振る舞いには、これ以上ないと言うほど魅了されており、そのモデルとして、私も名前は伺っており、以前から非常に興味はあった。
話によると、作者である板垣恵介が、範馬刃牙を描く前より交流があり、その人となりについて「才気のカタマリ」「爆笑した顔に狂気を感じた」「体中が地雷原のような人」などと評しており、以前板垣自身が武道家と立ち会い惨敗した話をした折には弟子に「その程度で済んで運がよかったと思え。二度と遊び半分の軽い気持ちで立ち合いに臨むな」と苦言を言付けたという。
塩田剛三が幼少の頃より柔道に邁進し、中学3年生にして四谷署の巡査たちを相手に5人抜きを達成、学級の対抗戦に至っては先方で出てチーム全員を総嘗めにし、段位は三段を取得。
まさに無敵を掘っていた塩田剛三だったが、その時の学校の先生の言葉に従い、合気道の開祖、植芝盛平の道場を訪ねることになる。
“開祖"植芝盛平
1人の壮年に、若い弟子たちが次々にかかっていてはいとも簡単に投げられて抑えられる様を見て、塩田剛三はインチキに決まっていると腹の中でセセラ笑っていたところ、やりませんかと持ちかけられ、どうやっても良いかと承諾を取り、掴みに行くふりをしていきなり蹴りを払ったと言う。
その瞬間、天地がひっくり返る、気づけば塩田剛三は植芝盛平に投げられていた。
それにより、塩田剛三のその胸中も、天地がひっくり返るような思いを抱えていたと言う。
腕っ節に自信のあったものが、小さな老人に訳も分からず宙に舞わされる。
小説や講談の中にしかありえないと思っていた、武道の妙技が存在した。
それから植芝道場に入門し、柔道の引く技から、合気道の押す力という点に戸惑いながらも、理合い、それを見極め、メキメキと上達していくことになる。
合気道とは一言で言ってしまえば、天地と一体となる、ここに尽きると言う。
事実、塩田剛三も、植芝盛平には手取り足取り教えられる事はなく、基本的には傍で見て、結構や結構やと言われ、何が結構なのかわからずに頭を悩ませていたと言う。
植芝盛平が実践していたのは、文字通りまさに実戦の中で花開く、武道としての合気道。
その一瞬、その一瞬にしか存在しない、その状況、相手の立ち位置、自分のなすべきこと、それを捕まえて、その一瞬の最大の効果を発揮する。
それを捕まえること、それこそが武道であり、二度と同じ状況は作り出せない、だからこそわかりやすい誰にでも理解できるような、そういった形というものを作ることも、示すこともなかったのだと言う。
事実、塩田剛三本人も、これでは才能がある者だけしか強くなれないとなかなか悩ましい事実として認めている一面もある。
その中心となるのが、呼吸力だと語っている。
呼吸力
呼吸力とは、事前概念としては理解しづらいものとも言えるが、自分の持っている能力を最大限に、最も効率強く使うところから生まれる力としており、そのためには体の軸を保つための中心力、動きの中で中心線を維持することによって生まれる大きな力――集中力、明鏡止水の果てにたどり着く無心、その場その場における最もふさわしいリズム、それらがピタッと一体になって発揮された時に、生まれる力だと言っている。
それらがうまくいったときに相手は抵抗力を失い、こちらにすべてを任せるような状態になる、協力してくれるような状態に導く。
まるで魔法のようにいともたやすく相手を制する、その凄まじく難解にして、到達が難しい原理、これですが、その一端だと言うのだから、驚愕と言えるだろう。
しかし塩田剛三に関して言えば、さらに恐ろしい事実がある。
その呼吸力の出し方として、様々な要素、さらにはその極意として、力を抜くとさえ語っている塩田剛三だが、その実、その実戦性に関しては、また全く違った方向の声明を発信している。
曰く、実戦では当身が7分。
これに関しては塩田剛三本人も、合気道と言えば手首を掴むもの、あるいは投げ飛ばすものと言うイメージに皆さんとらわれているようですから、驚かれた方も多いでしょうと語っている。
この言葉は植芝盛平から引き継いだようなものらしく、当て身が七分、投げが三分とし、実際に後輩を連れて新宿で30人以上のそっち系の人間と乱闘演じた際も、一触即発の中、一斉におそいかかってきたときに、それを先に塩田剛三が動き、腹に当て身を叩き込み、それに叫び声をあげて雪崩込まれるところに、自ら待つことなく向かっていき、サッと体を翻し、たたらを踏ませてぶつかり合わせ、自爆を誘い、そこを狙って次々と当身を叩き込んで行ったと言う。
正拳突きに関しても基本と述べて、著書の中で実戦でのKO率が高いのはこのストレートと断言し、瞬発力、膝の柔軟性、集中力、臂力の養成、拳の握り方と、合気道における力の使い方について深く言及しており、さらにその技は多岐に渡り、拳や蹴りなどのようにこだわりはなく、突進してくる相手を背中で弾き回したり、すれ違い様に肩で吹っ飛ばしたりと、体中至るところが武器となる語っている。
それを操る基本となる塩田広三の膂力は凄まじく、師匠である植島盛平に、バーベル上げやチューブトレーニングを本当につまらない運動だ、ああいうことをやるなと師事していた時は釘を刺されていたようだが、当人曰く、若さに溢れていた時分、エネルギーがありあまり、強くなりたい一心で、朝5時から夜9時までやれるだけの鍛錬をやって体をいじめ抜かないことには気が済まなかったと言い。
木村政彦をも越えた圧倒的膂力

具体的には腕立て伏せなんかも毎日250回位は軽くこなし、懸垂もその気になれば300回、片手懸垂は朝飯前、あの木村の前に木村なく木村の後に木村なしと謳われた、史上最強の柔道家、拓殖大学の同期、その怪力で250キロのバーベルを上げて、鉛の棒を捻じ曲げ、乗り遅れた弟子のために走り始めた都電の後ろにある牽引用の取っ手を掴んで引っ張り、電車を停車位置に戻してしまったこともあると言う木村政彦との腕相撲においても、身長170センチ体重85キロに対して、40キロもの体重差があったにもかかわらず、右手を握りあったまま、相手の気を伺い、元の合図とともに木村雅彦は力を入れる前に力を出し、力がゼロの状態でやられた木村政彦は勢い余ってひっくり返ってしまったと言う。
その時は木村雅彦も、何もしないうちに負けてしまったと苦笑いを浮かべたと言うが、実際のところ2人は10回やって10回木村政彦が負けたと語ったと言う話もあるが、ホントのところは3回やって、2回塩田剛三が勝ったと言うから、純粋な力比べでも五分以上と言って構わないものがあったのではないだろうか。
現在伝えられている、範馬刃牙を中心とした、渋川剛気を主とした、その魔法のように、幻想のように、相手をひらりひらりと躱して、空中に舞い上げる、その合気道の技術、しかしそれは単純な、凡人で理解できるような理屈から成り立っておらず、それは高い高い、われわれは見ることすら叶わないような雲上人の領域の、文字通り神業であり、そしてその根幹を支えるものは、想像を遥かに超えた、まるで太古の巨人のような、膂力から成り立っているのだった。
植芝盛平との立ち合い
塩田剛三は植芝盛平の内弟子時代、風呂に入られる時は必ず背中を流し、心の動きを速くキャッチして、それに対処する呼吸を会得しようとしたと言う。
桶を差し出し、言われる前にお湯をかけ、どのようにすれら満足されるか工夫する、いわゆる阿吽の呼吸。
そして稽古中においては植芝盛平の足の運びをじっと研究するも、袴を履いているため分かりにくく、必死で目をこらしたと言う。
さらには金魚鉢の縁をポンと叩き、パッと散る際互いにぶつからないでどのように避けているのか、しっぽのどこに重心がかかっているかを観察すると言うこともし、なんとそれは十年間にも及んだ言う。
他にもドアの上に棒を吊る下げておいて落ちてくるのを避けたり、人混みの中をぶつからないようにすいすい歩いたり、植芝盛平がなくなられた後は犬を師匠と思って修行を続けたりもしたと言う、ここまでくるとちょっとどうかしてるなと思いますけどねはい…
特に塩田剛三が龍と名付けた四国犬は極めて激しい気性で、本人以外には絶対に近寄らせず、人気のない公園に連れて行って話、自らにけしかけ、その飛びかかってくるのを交わし、最初のうちは手も腕も体も足も傷だらけになり、やめと言い、利口な犬に満足そうな顔をさせていたが、毎日行っているうちにだんだんと傷を負わなくなっていったと言う、皆さんにはお勧めしないと言っているが、果たしてこれを聞いてやる人はいるのだろうか…
そんな塩田剛三は拓大時代、柔道の木村政彦、そして空手の福井功とともに拓大三羽烏と呼ばれていたという。
当時無名であった合気道を修行していた塩田剛三がそのように認められるようになったエピソードとして、福井功は中山正敏や高木正朝とともに拓大に初めて空手部を作ったと言うが、喧嘩は強いが癖があり、柔道や合気道はどうってことないと触れ回っており、それを聞いた塩田剛三が、
じゃあ、やってみようか
と体育館で立ち会い、福井が右の正拳突きから前蹴りを狙ってきたところ、それを左へ避けて右腕で拳を挟むようにして左腕で左肘を叩いたらポン、と飛んでいったと言う。
それより福井がしばらく肘を痛め、その実績により塩田剛三は拓殖三羽烏の仲間入りを果たしたと言う。
その後拓殖大学を卒業した塩田剛三は軍部からの要請により中国、台湾、ボルネオ島などに派遣され、合気道の普及に努めたと言い、その出発の際子である植芝盛平にいつになく優しい目で、
塩田はん、あんたはだれにも負けんのやよ
それだけのものをワシはあんたに授けたんやから
しっかりやってきなさい
と言う言葉を承り、これ以上嬉しい事はなく、それまで怒鳴られるばかりだった塩田剛三にとってはじめての植芝盛平からのお墨付きであり、その言葉が心の支えとなり、以来誰と立ち会おうが遅れを取る事はなかったと言う。
そして昭和26年に合気神社の神前にて、植芝盛平直々に九段の審査を受けることになり、木剣では1歩も動けることができなかったものの、体術では隙を探り、余裕ができ、行ける!と思い下から顎を突き上げてやろうと思った瞬間によし、とみられ、立派なもんじゃと頷かれ、
剣はまだまだだが、体術がこれぐらいできれば良いじゃろう。
九段をやろう。
そのかわりこれからもっと剣を修行しなさい
と、その――植芝盛平本人からいただいた最後の免状を受け取ったと言う。
さらにその戦いの遍歴については、ある日見学に訪れ、最初は懐疑的だったものの本物であるがゆえに本物を見抜き、最終的に入門までに立ったと言う30歳を超えていたソ連のサンボ、レスリングの猛者である巨大のAさんにある日館長室に来て、
できればいちどだけ、その手を握らせていただくわけにはいかないでしょうか
つまりは技をかけてくれと言われ、気の済むようにしなさいと差し出し、塩嶺に恐縮を重ねる形だったために、
なんだい、この程度か。
あんた、体は大きいのにあんまり力がないねえ
と煽り、その結果満力のようなパワーで来たその瞬間、さっと手首を返し、180センチ、100キロ以上の巨体が1回転して、その人並外れたパワーが全て本人に返ってきて、館長室の床がその衝撃に揺れたと言う。
まさしく文字通りの、渋川剛気の再現――いや時系列的には逆か。
指を即剣と成し、肩で相手をひっくり返し、足の指一本で相手を制し、掴んだ手をくっつかせ離さなず、八対一の大男を手玉に取る。
その極意、タイミングについては、相手が100%の力を出すちょっと前、その出鼻をパン と叩くと話している。
これが決まったときの衝撃については、渋谷公会堂で演舞を行った際、その時点で警視庁の師範をやっている井上と言う男に木製の短刀で斬りかかられた際、横面打ちで受けると、短刀が吹っ飛んでいき、その木製の短刀がコンクリートの壁に突き刺さったと言い、さしもの塩田剛三も驚きを隠せなかったと言う話だ。
さらには小林拳の男が座っている塩田剛三に突きを放ってきたときに、その伸びきったところを狙って正面から手のひらを合わせて、後ろに吹き飛ばしたり、上海の街角ですれ違い様にジャックナイフで襲われた際、入り身でさばき、のびた腕を右手で引き、左裏拳を人中に叩き込み、地面をころげまわさせたり、埼玉県の朝霞キャンプで演武を披露している際、後輩がフックの一撃でK.Oされ、ハーイパパサーンと挑発されたために闘志を持って立ち向かい、ジャブをかわして懐に飛び込み、残った右手を取り、体を一旋させ、四方投げて叩きつけたりと、まぁなんていうか実戦でやりまくってますねこの人、正しく実践の雄、ケンカ合気道…
最後のジャブをかわして右手を取ったことに関しても、その左が牽制でしかなく、その後に狙う右のパンチを握っていたためにそちらを取ったと説明したりと、その動き、考え方は臨機応変、融通無碍そのもの。
そしてその投げ技は対柔道に対しても非常に有効で、道場を作る前、昭和26年に日本鋼菅にて柔道部の連中に真剣勝負のつもりで演舞に挑み、柔道6段の首相が掴みに来たところを四方投げの変形で腕を肩にかつぎ、肘を極めたまま投げて、ボキっと音をさせ、副将の柔道5段、関東大会優勝、空手3段、剣道3段、相撲3段の空手の突きをかわし、肘当て呼吸投げで投げ飛ばし、嘱託となったという。
ロバートケネディのボディガードを制しマイクタイソンに教授
その最も有名な逸話の1つとして、昭和37年にロバートケネディが養神館を訪れた際、その実力を試すために190センチ100キロのボディーガードの相手をし、座り状態から腕を取り、その瞬間にボディーガードは地を這わされ、何度やっても同じことの繰り返しで、その様子を用いロバートケネディは
その小柄な先生先生に私のボディーガードはまるでクモをピンで張り付けたよういとも簡単に取り抑えられてしまった――
と語っている。
そして平成2年2月7日には世界タイトルマッチを翌々日に控えた、WBA WBC WBF三団体統一王者であったマイクタイソンが訪れたと言い、その技を披露し、これら、特に呼吸投げに関して、これはタイミングの技であって決して力技ではないと話し、演武中その足運びに必死に目を凝らしていたと言う。
その力の出し方、極意について、塩田剛三は力を抜くことと語っており、師匠である植芝盛平に四ヶ条をかけ、もっと力を入れ、それくらいしか力がないのかと焚き付けられたそのチャンスに力を入れるふりをして、植芝盛平が力を抜いた、そこにサッと乗っかり、あの植芝盛平生コトンとひっくり返してしまったと言う。
その異常事態に植芝盛平はそんなバカなと言う顔をして見上げ、塩田剛三は1本とったと得意満面、後になりさっきの技は見事だったと褒めてくださったと言う。
合気道が試合がないと言うことに関しては、それを行えばルールの規制が生まれ、危険防止のために禁じ手が作られ、そうなったらもはや合気道ではなく、禁じ手がないからこそ護身術として効果を発揮すると述べている。
そしてその勝負論について、木村政彦が、試合はそのまま勝負だった、試合で負ける事は死ぬことと同じと思った、その覚悟でやっていたから試合では1度も負けた事はなかったと言う言葉を受けて、
死ぬといっても、死に直面したことのない人間には、その覚悟もわからんよ。
と語っており、
頭で理解してもらおうとしてもダメなんだ。
命がけって言う言葉は簡単だけど、それを実行に移すには自分をなくさにゃいかん。
とその深淵を言い表している。
さらにはその極意の1つである自然体について、
自分の方からこの技をかけてやろう、と気が先走ると技が後に来るから、そこにズレができる。
息との関連性がない。
しかし、呼吸と動作が一致すれば、後は相手との呼吸を合わせるだけで良い。
相手との動きに応じて自分が反応できるわけだ。
知らぬ間に相手の体を崩して、投げることができる。
これが自然体だ。
最終的にその究極の技、それを塩田剛三は
相手に敵対心を放棄させ、仲良くなってしまうこと、と話す。
生まれた時の素直な気持ちを持ち続け、大きな夢を持ち、肉の宮に神を宿し、歩く姿を武と成し、天地と一体となる。
その究極の理合いを突き詰め、その最後の言葉として
もう合気道が実戦で使われる必要は無い
私が最後でいいんだ
これからは和合の道として世の中の役に立てば良い
武道において最終的にたどり着く場所、到達点、そこに至ったものを達人と呼ぶ。
それは言葉としてあり得るが、常に学び続け、歩き続け、求道し続ける武道においては、そこに至る事はほぼないとされる。
しかし塩田剛三の思想、技術、そのあり方は正しく達人、それに呼ぶにふさわしく、余人には理解しがたい領域にあると言って構わないと考える。
___________________
おススメ記事!↓
関連記事はこちらへ!→ 空手及び格闘技




